がんとは:がんの生理学
腫瘍とがん
腫瘍とは「局所的に細胞が増殖してできた組織」のことである。この腫瘍には良性腫瘍と悪性腫瘍の二種類がある。悪性腫瘍がいわゆる「がん」である。
がんにも種類があり、がん腫瘍、肉腫、白血病・リンパ腫などがある。がん腫瘍は上皮性組織にできるがんのことで、肉腫は上皮性組織以外にできるがんのことである。また、白血病やリンパ腫は上皮性組織以外にできるがんであるが肉腫とは区別されている。
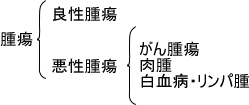
良性腫瘍はもとの組織構造が保たれており、きちんとした境がある。そのため、他の組織の場所を侵したり転移したりすることはない。また細胞分裂の際も正常に核が分裂し、染色体にも異常はない。
しかし悪性腫瘍の場合は組織構造に乱れが生じており、他の組織を湿潤する。細胞分裂は急速に行われ、無秩序に増殖する。
がんの形状であるが皮膚にできた場合は盛り上がり、臓器にできた場合は塊となる。血液性のがんの場合では正常でない血球や幼若血球が異常増殖する。
・がん細胞とは
①正常な細胞が変化したもの
②無秩序な増殖
③染色体構造に乱れのあることが多い
④他の臓器に転移・増殖する
⑤生体の免疫構造の感知不十分
がんの発生
がんはDNAに障害が起こるために発生する。DNAに障害があってもそれを修復することができれば全く問題ない。しかし、修復が完全でないとDNAが変異していく。この「DNAの変異」が蓄積していくとがんになる。
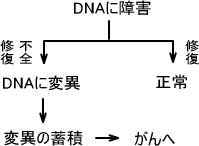
がん発生には環境要因が大きく関係している。つまり発癌物質、ウイルス・細菌、放射線・紫外線などによるものである。
発癌物質といって身の回りには多くの発癌物質が存在する。例えばコールタール(すす)があり、これはコールタールに含まれる発癌物質のベンツピレンが原因である。他にもカビからのアフラトキシンB(黄カビが産出)などがある。
・喫煙と発癌
喫煙と肺がん発生率には相関がある。つまりタバコと肺がんには比例関係がある。タバコの本数が多いほど、若年での喫煙開始が早いほど肺がん発生率が上昇する。
タバコの本数 ∝ 肺がん率
若年での喫煙開始 ∝ 肺がん率
食事とガンの関係
ヒトのがんと食品は大きく関わっている。がんと食品の関係の良い例としてハワイ日系人の例がある。ハワイ日系人は遺伝子は日本人であるが、生活はアメリカ人の生活であるためアメリカ型の発癌を生じるのである。
日本の食生活は肉消費が多くなり欧米化しつつある。それに伴い、胃がんの発生率は減少しているが大腸がんの発生率が増加している。
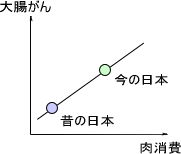
※日本人に胃がんが多いのはピロリ菌や食塩の関係である。
食品に含まれる発癌物質には天然由来のもの、人工的に混入したもの、加工により生成したもの、カビが産出したものなどがある。
また、発癌物質にもそのままの構造でDNAを損傷させる直接発癌物質と代謝などによって構造が変化することで活性化し、DNAを損傷させる間接発癌物質の二種類がある。
例えば、ソテツの実にはサイカシンという発癌物質が含まれているが、この物質は体の代謝酵素によって代謝されることで活性化する。
細菌・ウイルス発癌
それぞれ次のような細菌・ウイルスががんを誘発させる。
ヘリコバクター・ピロリ … 胃がん
C型肝炎ウイルス … 肝がん
パピローマウイルス … 子宮がん
ヒト白血病ウイルス(HILV) … 白血病
EBウイルス … バーキットリンパ腫
放射線発癌
放射線発癌は宇宙線、医療X線、紫外線などが原因で起こる。
人為的に放射能汚染が起こった事件ではチェルノブイリ原子力発電所事故が有名である。多くの放射性同位体がばら撒かれ、事故周辺地域では小児甲状腺発癌率が上昇した。
スポンサードリンク
カテゴリー
スポンサードリンク
